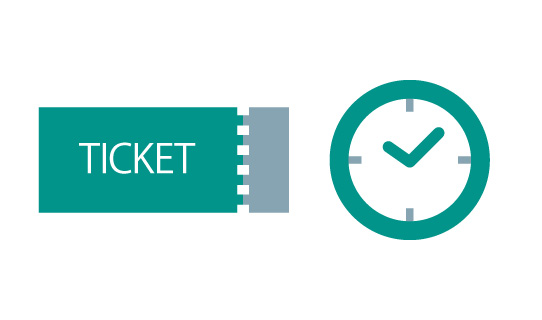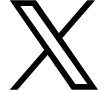交通教育センタートップ企業・団体向け安全運転研修オーダーメイドプラン
時間とコストをかける研修は、その開催そのものが目的ではありません。
限られた資源の中でいかに効果を出すかを専門の担当者が皆様とともに考え、
私共が蓄積してきた実績と、社内データを突きあわせ、ヒアリングを重ねながら
各社オリジナルの研修プログラムを組み立てます。


Hondaと鈴鹿サーキット交通教育センターが開発した
独自の運転評価システム(HDSP※1)を活用した「運転習慣チェックプログラム」
※1 HDSP:HONDA DRIVING STYLE PROPOSAL SYSTEM
運転評価システム(HDSP)の特徴
- 運転者自身による「自己評価」と評価システムによる「客観評価」をデータで比較。
- 比較した結果と総合的な分析結果から見出される「認識の差異」の存在と大きさを明確化。
- 今後の課題と必要な取組みの具体的化と、効果分析が可能。
-

システムによる運転評価
-

自己評価
-

評価結果検証
「運転習慣チェック」による効果
- 現状把握 一人の運転者の位置づけと、参加した部門や、事業所の位置づけがみえてきます。
- 課題設定 目指すレベルを明確にし、そこに向けた教育や環境づくりにつなげていただけます。
- 教育効果検証 定期的な測定で、日頃の成果を確認でき、あらたな課題も見つかります。
-

交通事故の報告書で目に付くコメントは、「車間距離をとっていたけれど追突した。」「考えごとをしていて追突した。」「停止中に追突された。」でしょう。
当事者にとっては「十分だった車間距離」も、その目安は不明確なことが多いものです。
また、意識の脇見や、被追突もあきらめる訳にはいきません。なぜ、どうして、だから、誰が、なにを、どのように、どうするか。実技研修で記録した各自のデータをもとに理論を通して考えていただくことにより、役に立つ具体的な数字と行動を導き出していただきます。 -

この悩みを抱える企業は多いものです。中にはその都度修理することをあきらめてしまう企業も存在しますが、小さな事故はいつか取り返しのつかない重大事故に発展します。そうなる前に、「小さなミスも見逃さない意識」を社員一人ひとりが持てるよう、実技研修の中から見えてくる、目配りや気配り、行動の省略などから考えていただきます。クルマの車両感覚や狭い場所での運転操作を習得するだけでなく、「今どこに注意するべきなのか」「狭い場所での安全な運転とは何か」といった安全マインドも高めます。
-

たいへん悩ましいケースですが、「繰り返す」ことが分かっていながら運転を続けさせることは、企業の社会的責任としても見逃すことができません。
マンツーマン研修や少人数研修で、「自分の運転は安全なのか」を客観的に評価して、繰り返す原因や対策を見つけ出すことが必要です。研修を通して事故に結びつく疾病がみつけ出されることも あります。


 降雨装置を使用した夜間研修
降雨装置を使用した夜間研修
研修を終えた直後は良かったのに、「いつのまにか元に戻ってしまった。」というお話を伺うこともあるのが現実です。本人がやる気になっても周囲がそのやる気を削いでしまえば、研修に投じた時間もコストもムダになります。現場で本人の味方となれる人づくりは欠かせません。そこで必要となるのが企業内の指導者です。管理職に限らず先輩となる層を指導者として養成することもお勧めします。
- 1日目
- 10:00開講式
- 10:30ディスカッション(企業のドライバーが意識すべきこと)
- 11:00運転習慣チェック(現状把握)
- 12:00昼食
- 13:00基本動作(会社のクルマの取り扱い)
- 14:00狭路走行(駐車場や狭い道路での対応)
- 17:00座学(交通危険予測)
- 18:00夜間検証19:30
- 2日目
- 7:00高速道路走行
- 8:00朝食
- 9:00車間距離検証(急ブレーキとハンドル回避)
- 10:30意識の脇見検証
- 12:30昼食
- 13:30運転習慣チェック(研修効果確認)
- 14:30グループディスカッション
- 15:30決意表明
- 16:00閉講式16:30
日程、使用する車両などはお問い合わせください。