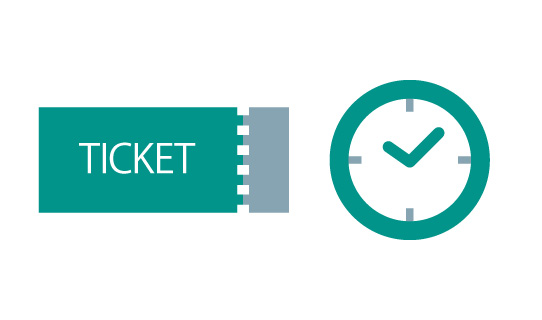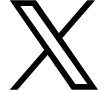2025/08/22
知ると面白い “Intercontinental GT Challenge” 9メーカーが競い合う長距離GTレースの最高峰レース
インターコンチネンタルGTチャレンジを創設したのは、元レーシングドライバーでもある、ステファン・ラテルが創業者兼CEOを務めるSROモータースポーツグループ(通称:SRO)。同社はこれまでFIA GT1世界選手権やブランパン耐久シリーズを立ち上げ、2020年からはFIA-GT3車両によるGTワールドチャレンジ・パワード・バイAWSで成功を収めてきた。
そのSROモータースポーツグループが『世界最高峰の独立耐久レースで最高の総合成績を達成したメーカーとドライバーに報酬を与える』ために、2016年に設立したレースシリーズがインターコンチネンタルGTチャレンジだ。
シリーズは"長距離GTレースの最高峰"と位置づけられ、レースカレンダーも大陸を跨ぐかたちで形成されている。2025年はオーストラリアでのバサースト12時間を皮切りに、ドイツのニュルブルクリンク24時間、ベルギーのスパ24時間、日本の鈴鹿1000km、そしてアメリカのインディアナポリス8時間という計5大会を開催。レースの合計は76.5時間にもおよぶ。
レースは近年世界で隆盛を誇るFIA-GT3車両で争われ、タイヤはピレリのワンメイクとなるが、参戦メーカーは世界各国から威信をかけたマシンを送り込む。なかでもBMW、フェラーリ、メルセデス、ポルシェの4メーカーはインターコンチネンタルGTチャレンジにフルシーズン参戦を行い、総合優勝とチャンピオンの座をかけて、長距離レースながら、スプリントのような緊張感でメーカー争いを繰り広げている。
今季は上記4メーカーに加え、アウディ、アストンマーティン、シボレー、フォード、マクラーレン、ランボルギーニも参戦しており、鈴鹿1000kmの前戦となるスパ24時間には10車種、合計76台がエントリーを行った。またメーカーは、自前のワークスチーム*ではなく、各地域のカスタマーチーム*をサポートするかたちでの参戦となるため、車両の輸送費用を抑えることができることもポイントだろう。
シリーズの得点配分は、参戦する全GT3マシンがポイント獲得対象となるが、マニュファクチャラー*ズランキングには上位2台のみが加算される。ただし、ドライバーズチャンピオンシップにはこの制限はなく、クラスごとに純粋な速さを競うものになっている。また、アマチュアドライバーには"インディペンデントカップ"*と呼ばれる栄光が授与される。
マニュファクチャラーズランキングを2016年から振り返ると、初年度から2018年まではアウディが3年連続でタイトルを奪っていたが、2019〜2020年はポルシェが王者に。2021年には再びアウディがタイトルを奪還したものの、2022〜2023年はメルセデス、2024年はポルシェがマニュファクチャラーチャンピオンに輝いており、創設からすべての王座をドイツブランドが占める強さをみせている。
日本の自動車メーカーは、トヨタGRがレクサスブランドのRC F、HondaはNSX、ニッサンはGT-RをベースにしたGT3マシンで参加していたが、近年のインターコンチネンタルGTチャレンジには参戦していなかった。しかし、2025年はニッサンGT3マシンの参加が発表された。今年は世界のスーパーカーに挑む日本車の姿を見られる。
また、近年の参戦チームは自動車メーカーが技術面やスタッフを支援する"半ワークス体制"が多く、各チームのドライバーも世界で活躍するメーカー育成選手が名を連ねている。そういったこともあり、インターコンチネンタルGTチャレンジの一戦として争われる9月の鈴鹿1000kmでは、各マニュファクチャラーの"エース級ドライバー"が数多く参戦することになりそうだ。
ワークスチーム:自動車メーカー自身が直接運営するレーシングチームのこと
カスタマーチーム:各メーカーのGT3車両を購入して、レースに参戦する独立系チームのこと
マニュファクチャラー:自動車メーカーのこと
インディペンデントカップ:アマチュアドライバーが年間ポイントを競う部門のこと