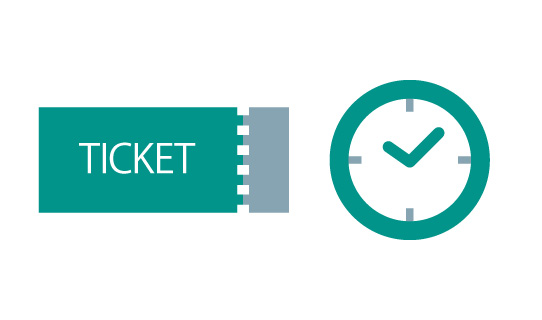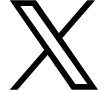2025/08/08
今季のIGTCを数字で振り返る
レースは"1000km"到達を目指す"6時間30分"にわたって行われるタイムレース。ちなみに1000kmという距離は、東京〜大阪間を往復すると考えればイメージがつきやすいはず。なお、今回のイベントで使用されるFIA-GT3マシンは燃費や1スティント*"65分"というひとりのドライバーの連続最大運転時間となるため、約1時間に1回のピットインが必要になると考えられることから、レースは"6回ピットストップ"の"7スティント"が基本戦略になることが予想される。
*スティント:ドライバーがピットインせずに連続して走行する区間のこと
そのピットストップでは『最低ピットストップ時間』が決められていることも特徴だろう。通常の国内レースではピット時のストップ時間は定められていないが、さまざまなGT3車両が争うインターコンチネンタルGTチャレンジでは、ピットレーンに入ってからピット作業を行い、コースに出ていくまでの最低ピットストップ時間が決められている。この時間は大会によって変わるが、2019年の鈴鹿10時間耐久レースのときは"83秒"に定められていた。これにより車種による燃費や給油時間といった有利不利が極力減らされているのだ。
"5大陸"にまたがって争われるインターコンチネンタルGTチャレンジの一戦ということもあり、参戦チームもバラエティに富んだものになるだろう。前戦のスパ24時間レースにはアウディ、アストンマーティン、シボレー、BMW、フェラーリ、フォード、ポルシェ、メルセデス、マクラーレン、ランボルギーニから10車種の"合計76台"がエントリーした。 >>2025鈴鹿1000km エントリーリストはこちら(PDF:244KB) また、通常のGT3レースなどでは1チームで多くて2名のドライバーが登録されるが、鈴鹿1000kmではレース距離が長いことから、ほぼすべてのチームが1台あたり3名のドライバーで参戦することになる。2019年の鈴鹿10時間耐久レースでは、36台という参戦車両に各チーム3名が乗り込み、ドライバーの人数は"17カ国"から"108名"が名を連ねた。
そして、インターコンチネンタルGTチャレンジはドライバーの実績や実力によってプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズという4つのカテゴリーに分類されており、レースもドライバーの組み合わせごとに『PRO』『PRO-AM』『SILVER』『AM』の"4クラス"に分けられている。
今年の鈴鹿1000kmでも、世界のGT3レースを戦う自動車メーカーのワークスドライバー*はもちろん、ふだんGT3とは異なるレースを戦っているプロドライバー、そしてアマチュアドライバーまで、さまざまなドライバーが日本有数のドライバーズコースである鈴鹿サーキットを走ることになるはずだ。
*ワークスドライバー:自動車メーカーと直接契約を結び、そのメーカーを代表してレースに参戦するプロのドライバーのこと